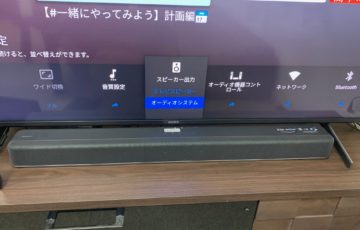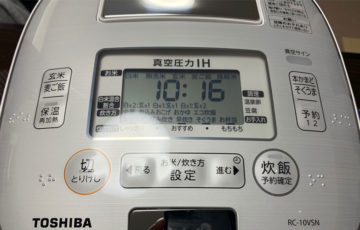お彼岸は年に2回あります。
春のお彼岸と、秋のお彼岸ですね。
お彼岸には、ぼた餅をお供えしたり、お墓参りに行ったりするものですが、普段からこういった習慣に馴染みがないと、お彼岸の時期がいつ頃なのか曖昧だったりするものです。
では、春のお彼岸の時期についてみていきましょう!
春のお彼岸は春分の日と立春のどっちが正しい?
春のお彼岸は春分の日と立春のどっち?
正解:春分の日
春のお彼岸は春分の日が基準となります。
春分の日を基準に、前後3日間を含めた7日間が春のお彼岸ということになります。秋のお彼岸も同様に、秋分の日を基準にして、前後3日間を含めた7日間が秋のお彼岸になります。
春分の日と秋分の日は、昼と夜の長さが同じになる日(正確には昼の方が14分ほど長い)としても知られていますが、太陽が真東から昇り真西に沈む特別な日でもあります。こういったこともお彼岸の時期の由来に関係してくるようですね。
春分の日と立春の違い
春分の日は3月20日~21日頃、立春は2月3日~5日頃となりますので、同じ「春」という文字が使われているものの、時期的には1ヶ月半以上違ってきます。立春はお彼岸とは無関係で、前日が節分という位置付けになってきます。
春分の日 → 春のお彼岸の中日
立春 → 前日が節分
「暑さ寒さも彼岸まで」ということわざがありますが、春分の日と秋分の日が目安だとすれば納得ですよね。3月も下旬となれば暖かくなる時期ですし、9月の下旬になれば暑さも落ち着いてきます。立春も暦の上では春のはじまりとなりますが、実際には2月の初旬で冬真っ只中です(笑)
春分の日は毎年変わる?
春分の日は国民の祝日となっています。
正確な日付は制定されていません。その年によって違ってくるわけですが、3月20日か3月21日のどちらかになることがほとんどです。ただし、これ以外の日付になる可能性もあります。
春分の日の正確な日付は、前年2月1日に歴要項(れきようこう)が官報に掲載されることで分かる仕組みになっています。もちろん、春分の日が1日ずれれば、春のお彼岸も1日ずれることになります。
歴要項(れきようこう)とは?
国立天文台が毎年2月最初の官報に掲載する、翌年分の暦に関する事項をまとめたもの。
春のお彼岸にすることは?
お墓参り
お彼岸と言えばお墓参りです。
ちょうど春休みの時期でもありますし、出来るなら家族揃ってお墓参りに行きたいところですね。そういった習慣が、子供たちの世代にもずっと引き継がれていくものです。

ご先祖様を敬う
お仏壇の掃除はお彼岸の入りまでには済ませておきましょう。
お墓参りに行った時は、もちろんキレイにお墓の掃除もします。ご先祖様や亡くなったご家族の事を敬い、お供えをしてお参りしてあげましょう。
お彼岸の期間には、彼岸会という法要が行われたりもするので、タイミングが合えば参加していみるのもいいですね。亡くなったご家族もきっと喜んでくれます。
ぼた餅とおはぎ
春のお彼岸には「ぼた餅」、秋のお彼岸には「おはぎ」をお供えして頂きます。これ、言い方は違いますけど、同じ食べ物のことですよね。ぼた餅は春の花「牡丹」、おはぎは秋の花「萩」が名前の由来と言われています。
ぼた餅には他にも夏の呼び名や冬の呼び名もありますが、こちらはほとんど知られていません。和菓子屋さんなどでも春に「おはぎ」として売られていたりもしますので、呼び方にはそれほど固執する必要はないのかもしれませんね(笑)
今回のまとめ
春のお彼岸は春分の日と立春のどっちが正しい?
これは「春分の日」が正解でした。
一度知っておけば何てことの無いことですが、春分の日と立春は勘違いしやすいので気をつけたいですね。立春は暦の上では春のはじまりですが、実際にはまだ寒い冬の時期で、この立春の前日が節分ということになります。
春のお彼岸は、春分の日の前後3日を含めた7日間です。
あとがき
家庭によっては、お彼岸などの風習に触れる機会が少ないこともあります。まさに私の家がそういった家庭でしたが、テレビの「サザエさん」で何となく季節ごとの風習を知ったものです。お彼岸のお話では「ぼた餅」や「おはぎ」が必ず登場していましたね。本当に美味しそうに見えたものです(笑)
いつだったか、カツオとワカメが「ぼた餅」と「おはぎ」の呼び方で揉めていたお話がありましたが、波平が登場してきて「牡丹」や「萩」の話しも交えて由来をきっちり説明していました。「サザエさん」にはこういった豆知識がちょいちょい登場します。
家族揃ってみたいアニメですよね。
ということで、春のお彼岸と春分の日のお話でした!